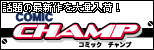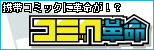第一回「ダメ男事件ファイル」
最終審査通過作品は、
大森ろらさん作「ダメ男事件ファイル」!!
最終審査通過作品は、
大森ろらさん作「ダメ男事件ファイル」!!
最終審査員 吉本新喜劇女優 末成由美
|
エピソードの女王受賞作 氏名(ペンネーム) 大森ろら 年齢 36歳 湊からメールが来て(あとでうち来るんだったら、コンビニでハーゲンダッツのストロベリー買ってきて)って。 昨日徹夜して描いたイラストはさっき会社にもっていった。小さな会社だけど、時々仕事をまわしてくれて、けっこうギャラもいい。っていってもたかがしれてるけど。わたしは正真正銘の貧乏。月二万、共同トイレのぼろアパートに住んでいる二十八の女だ。 彼氏の湊は同い年で、中学校の同級生。中ニの夏、花火大会デートでキスをして付き合い始めた。湊はけっこうかっこ良くて、女の子にも人気あって、勉強もそこそこできて、難しい本とか読んでて、サッカーも上手で、転んで膝から血がでたら女子ギャラリーがぎゃあぎゃあ喚いて、なんなの暴動起こっちゃうの?ねえ、起こってしまうわけ?みたいなぐらい、輝いていた。だから、わたしは湊の彼女になれたときがたぶん人生のピークだった。 湊には両親がいなくて、ずっとおばあちゃんとふたりで暮らしている。両親は彼が小学生の時に離婚して、どちらも彼をひきとろうとしなかった。だから湊は高校を卒業すると就職した。けれど、一ヶ月で辞めた。理由は「詩人になるから」だった。オーマイガ。 以来、彼はニート。自称詩人のニート。おばあちゃんの年金で暮らしている。おばあちゃん、今、七十ニ歳。 わたしはコート着て財布もって、ぼろアパートを出る。湊は一日なにしてるかっていうと、昼間はオンラインゲームをしている。小学生とか同じニートとかと戦っている。そして夜になると読書したり詩を書く。手作りの詩集はもう何十冊にもなってて、わたしも何十冊ももらっている。お誕生日とかクリスマスにプレゼントしてくれるのだ。もちろん全部読む。感想も言う。 「おまえは一応プロの仕事してるし、そういうプロの意見が聞きたい」とか彼は言う。 詩のことは正直わからない。彼の詩は散文に近いとおもう。なんか日記みたいだから。 「ねえ、湊。長い文章を書いてみたら?つまり小説。自分がこれまで生きてきたことをまとめてみるの。ありのままに。けっこういいものが書けるとおもうけどな」 「おれは詩人なんだ」 なるほどそうでした。ニート詩人。OK。了解。把握。 もう冬で、マフラーを忘れたから首が寒くて身を縮めながら歩く。そして、つい数日前に某出版社のN氏とのあいだに起こった出来事を思い出す。三十歳のN氏はわたしがもちこんだ絵を褒めてくれて、ポストカード形式の絵本にする企画の候補にあげてみようと言ってくれた。その打ち合わせもかねて今夜飲めるかと誘われたのでもちろんOKした。 そこは小綺麗なダイニングバーで、個室を選んだN氏はなぜかわたしの横に座り、わたしの肩を抱き、注文したカナッペやカクテルには手もつけずに、「キスしてもいいかな?」とわたしの耳元で囁いた。わたしは慌てて荷物をもって逃げ出した。逃げてその足で湊の家に行った。 「え、なんかすごく顔色が悪いよ」 湊はわたしの冷たい頬に触って驚いたように言った。わたしはうなずいてからあったかい居間にはいって炬燵のなかで横になった。 わたしは心のどこかでちょっと、もしかしてN氏ってわたしの運命のひとじゃないかなんておもったのだった。絵を褒めてくれて、飲みに誘ってくれたとき、わたしは確かになにかを期待していた。でも期待していたものは肩を抱かれてキスすることじゃなかった。 湊のあたたかい手がわたしの肩にそっとおかれた。手に力がそっとこめられると、こわばった体が中心からほぐれていく感じがした。 彼はこの先も死ぬまでちゃんとした仕事につくことはないだろうし、おばあちゃんが死んだら食うに困る。わたしが面倒を見るしかない。わたしはイラストレイターを続けながらなにか仕事をしなければいけなくなるだろうし、もしかしたら、絵を諦めなければいけなくなるかもしれない。 悲観しているわけではない。楽観もしていない。ただわたしは、現実の話をしている。自分が選んだ現実の話を。 コンビニでハーゲンダッツのストロベリーとチョコ、それからおばあちゃんのためのチータラを抱えてレジにもっていく。 「スプーンはおつけしますか?」 「はい」 「ふたつごいりようですか?」 「はい」 コンビニを出たら、自然と駆け足になっている。寒いからそんなにすぐにアイスはとけないことはわかっている。けれど、わたしは力強く地面を蹴る。 佳作は以下の4作品です。おめでとうございます。 ・『はじめての彼』 原キリコ(20歳) ・『教祖』 柴田めぐみ(29歳) ・『困ったインド人との出会い』 よくねるこ (35歳) ・『竜宮城』 乙姫 (32歳) |